医療DX推進体制整備加算について
当院では
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療提供の取り組みをしています
・電子カルテ情報共有サービスなどの取り組みをしています
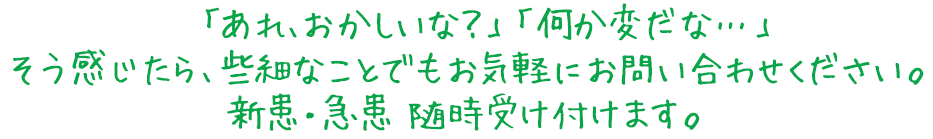
宮城県亘理郡亘理町にある大友医院小児科・耳鼻咽喉科は小児科・耳鼻咽喉科専門のクリニックとして
大切な地域の子供たちの健康を守ることは当然として、
ご両親の抱える不安を取り除くことにも全力で取り組んでおります。
高熱などの突発的な病気の際はもちろん、「あれ、おかしいな?」「何か様子が変だな?」と
感じた時には些細なことでも結構ですのでお問い合わせください。
地域の子供たちが笑顔でいられるよう、スタッフ一同励んでまいりますので、
病気のことに限らず、何でもお気軽にご相談ください。
当院では
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療提供の取り組みをしています
・電子カルテ情報共有サービスなどの取り組みをしています
当院では
大友医院
休診などの予定はカレンダーに記載しております。
ご迷惑をおかけしますが、ご確認をお願いいたします。
カレンダーに表示されていない場合はお問い合わせください。
当院で働いてくださる看護師さん、または准看護師さんを募集しています。
詳しくは、
診療時間内に0223-34-3204まで、お電話でお問い合わせ下さい。
************************************************
月 8:30~12:00
火 8:30~12:00/13:30~17:00
水 8:30~12:00
木 8:30~17:00/13:30~17:00
金 休診
土 8:30~13:00
日・祝日 休診
************************************************
当面は受付いただいた順番で診療いたしますが、混雑の具合により今後予約制の導入も検討いたします。
また、開設してまもなくは、
・通常以上にお待たせしたり
・検査に時間がかかったり
等、混乱をきたす可能性もございます。
何卒ご了承いただけますようお願い申しあげます。
*繰り返しになりますが、
発熱・のどの痛み・咳・鼻水などの風邪症状のある方は、
診療時間内に 0223-34-3204 まで事前連絡くださいますようお願いいたします。
風邪症状のある方は、正面入り口からは入れません。
どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
小児科 診療時間変更について
耳鼻咽喉科 診療時間変更について